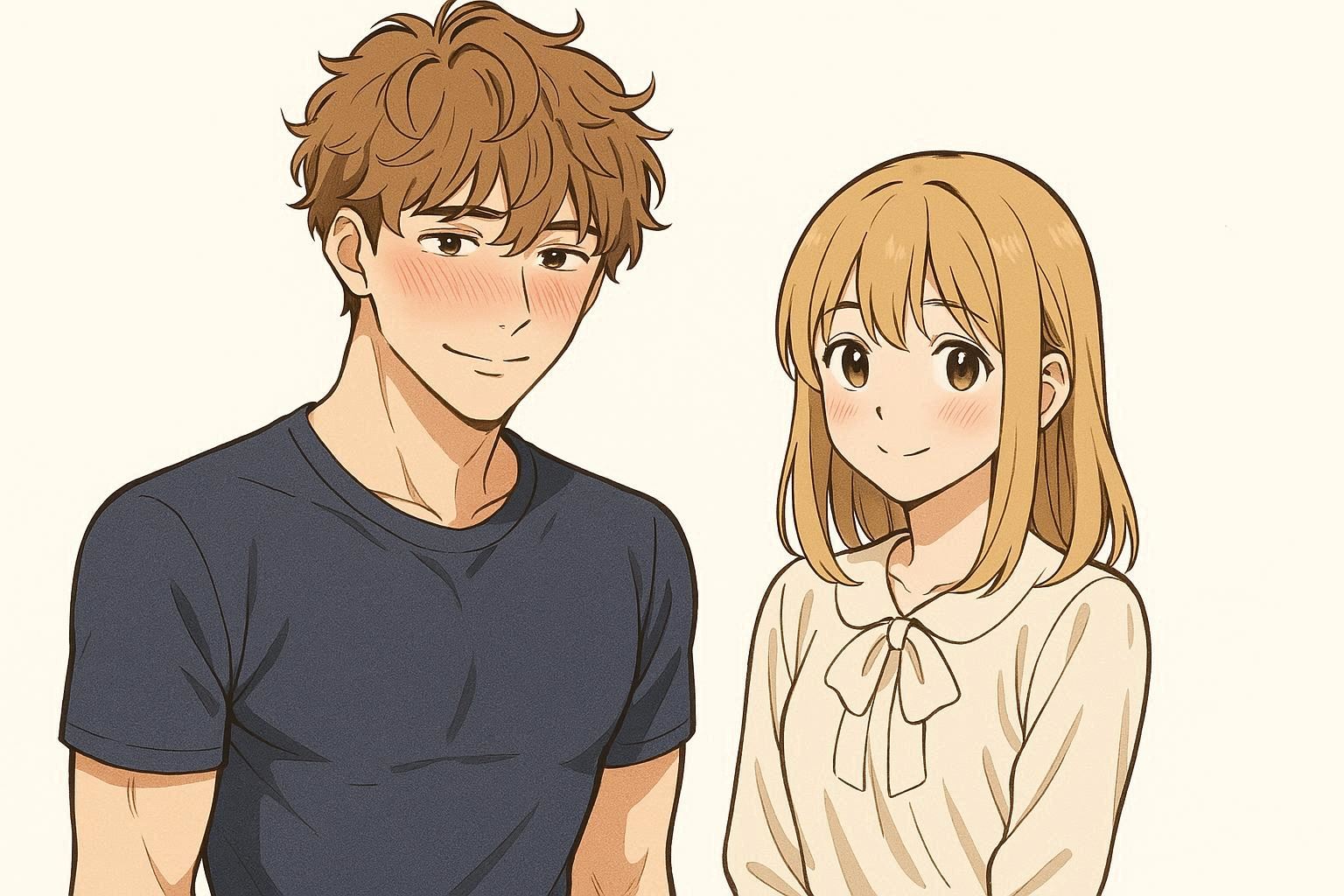0|安い国ニッポンの現実
いま日本では、多くの人が「生活が苦しい」と感じている。
2025年現在、スーパーの食材、光熱費、外食の価格は軒並み上昇し、特に都市部では家賃や交通費の上昇も顕著だ。
しかし、賃金はそれほど上がっていない。実質賃金指数は20年前より低く、手取りの減少を肌で感じる人が多い。
「安い国ニッポン」と言われるようになって久しいが、皮肉なことに、今では日本人自身がその“安さ”を享受できない。
観光地では外国人観光客が爆発的に増加し、円安の影響で彼らにとっては“格安”な商品や宿泊施設も、日本人には“高くて手が届かない”存在となっている。
京都では「外国人に占領された」と感じる住民が増え、飲食店や宿泊施設が外国人客優先で日本人を断る例も報じられた。
この現象の背景には、単なる為替変動や観光ブームだけでなく、長期的な賃金停滞と税制による可処分所得の圧迫という構造問題がある。
本稿では、1990年代以降の経済と政策の流れを時系列でたどりながら、「なぜ日本人は貧しくなったのか」を明らかにしていく。
1|バブル崩壊から始まった「失われた成長」
1991年のバブル崩壊は、日本経済の転換点だった。地価・株価が急落し、金融機関は不良債権を抱えた。
その後の「失われた10年」、さらには「失われた30年」と呼ばれる時期には、経済成長率がほぼゼロに近い状態が続いた。
政府は景気対策として公共事業を拡大したが、構造的な改革には踏み込めなかった。
デフレ(物価が継続的に下落する現象)が定着し、企業は賃上げよりもコスト削減を優先。
正社員雇用が減り、非正規雇用(ひせいきこよう)と呼ばれる短期契約・パート・派遣労働が拡大した。
非正規の比率は1990年代初頭の約20%から、2020年代には40%近くにまで上昇。
これにより、年収200万円以下の層が激増し、「ワーキングプア(働く貧困層)」という言葉が定着した。
この時期、日本社会は“働いても豊かになれない”構造を内包し始めた。
2|税制と社会保障が家計を直撃
1997年、橋本内閣のもとで消費税率が3%から5%に引き上げられた。
この決定は、当時景気が回復基調にあった日本経済を一気に冷やした。
消費税(value-added tax)は、所得にかかわらず全員が同じ税率で負担する「逆進性(ぎゃくしんせい)」を持つ。
つまり、低所得者ほど負担感が重くなる税なのだ。
以後、2014年に8%、2019年に10%へと段階的に引き上げられた。
さらに、社会保険料(年金・医療・介護)の個人負担も増え続け、所得税や住民税の控除範囲も縮小した。
結果として、名目賃金が上がっても手取りは減る「可処分所得の減少」が進んだ。
企業にとっては社会保険料負担の増加が雇用コストを押し上げ、正社員を減らして非正規に置き換える誘因となった。
家計も企業もともに“重税感”に苦しむ構造が、ここで固定化された。
3|グローバル化と円安がもたらした価格の歪み
2000年代以降、グローバル化の波が日本経済を覆う。
企業は生産拠点を中国・東南アジアへ移し、国内では空洞化が進んだ。
安価な輸入品が流入し、国内物価は下落したが、同時に国内産業の賃金競争力が削がれた。
2020年代に入り、世界的なインフレと円安が重なった。
1ドル=160円台に達した2024年には、海外から見れば日本の物価は“破格の安さ”だった。
外国人観光客にとっては魅力的でも、日本人には「給料が安すぎて買えない」という現象が生じた。
経済学では、こうした現象を購買力平価(こうばいりょくへいか)の観点から説明できる。
購買力平価とは、各国の物価と為替レートの関係を示す指標で、
同じ商品がどの国でどれだけの通貨で買えるかを比較するものだ。
日本では賃金が伸びないまま円安が進行したため、購買力が極端に低下した。
結果として、企業は外国人向け価格を設定し、日本人をターゲットから外すようになった。
これが、現在の「インバウンド偏重経済」である。
4|観光立国の陰で進む「日本人排除」
2023年以降、コロナ規制が緩和されると外国人観光客が急増した。
観光庁の統計によると、2025年には年間3,800万人を突破し、史上最多を更新した。
特に京都、富士山、浅草などで観光地が混雑し、「オーバーツーリズム(観光過剰)」が社会問題化した。
オーバーツーリズムとは、観光客の過剰流入によって地域の生活環境や文化が破壊される現象を指す。
京都では民泊やホテルの建設が相次ぎ、家賃が高騰。
地元住民が中心部から追い出される「ジェントリフィケーション(高級化による住民排除)」が進んだ。
飲食業界でも、外国人観光客を想定した価格設定が常態化し、
一部の老舗料亭や旅館では「外国人価格(higher foreigner price)」を導入する例まで見られた。
これらの現象は、グローバル資本が地域経済を呑み込む典型例である。
一方で、外国人観光客の支出はGDPを押し上げ、輸出と並ぶ重要な経済項目になった。
このため政府は観光促進を続けたが、結果として「日本人の生活空間が観光資本に奪われる」という逆説的な事態を生んだ。
5|中間層の崩壊と「貧しさの常態化」
厚生労働省の統計によれば、日本の実質賃金は1997年をピークに下がり続けている。
この約30年で、平均年収は実質ベースで15%以上減少した。
一方で、税や社会保険料の負担は増加。
結果として、手取りは1970年代よりも少ないという家庭すらある。
教育費や住宅ローン、老後の備えといった生活コストが増えたことで、
中間層(middle class)は薄まり、格差社会(inequality society)が定着した。
富裕層と低所得層の二極化が進み、「努力しても報われない」と感じる人が増えた。
社会学では、このような現象を「社会的排除(social exclusion)」と呼ぶ。
それは単なる貧困ではなく、社会の主流から外される構造的現象である。
経済的困窮は、教育格差・健康格差・文化格差を生み、
貧困が世代を超えて連鎖する「構造的貧困(structural poverty)」へと変わっていった。
6|税と物価の二重苦を超えて
日本の物価高騰と税負担の問題は、一時的な景気変動ではなく、
30年以上にわたる構造的停滞の結果である。
賃金が上がらない一方で、消費税と社会保険料が増え、
円安が進み、外国人需要が国内価格を押し上げた。
その帰結として、日本人は自国での観光・外食・購買すらためらうようになった。
もはや「安い国」ではなく、「自分の国で暮らしにくい国」になっている。
本来、税制とは国民の再分配を通じて生活を安定させる仕組みである。
しかし現実の日本では、再分配が逆流し、負担が下層に集中している。
この構造を是正するには、単なる減税ではなく、
労働分配率の改善・社会保険の再設計・地域経済の再生が必要である。
経済学的には、日本が目指すべきは「成長よりも生活の質の向上」であり、
政治的には「誰もが自国の中で dignified(尊厳ある)生活を営める社会」である。
この国の物価高は、単なる数字ではない。
それは、長年にわたる政策の歪みと、国民の努力が報われない構造を映す鏡である。
そして、その現実を直視し、未来の世代が同じ苦しみを味わわないようにすることこそ、
いまを生きる私たちに課せられた責任なのである。